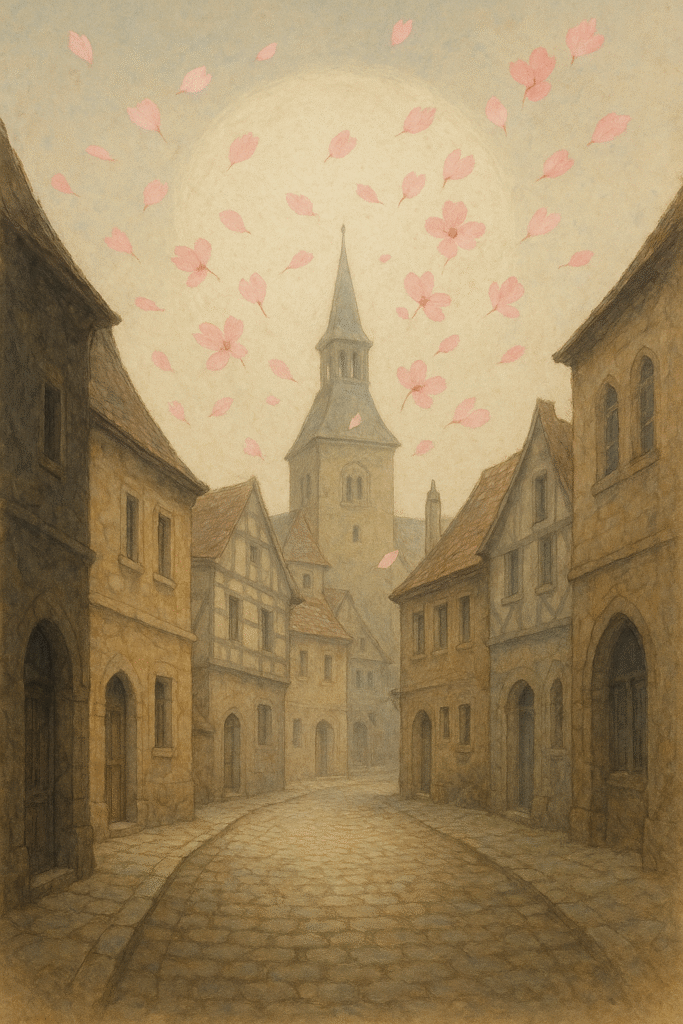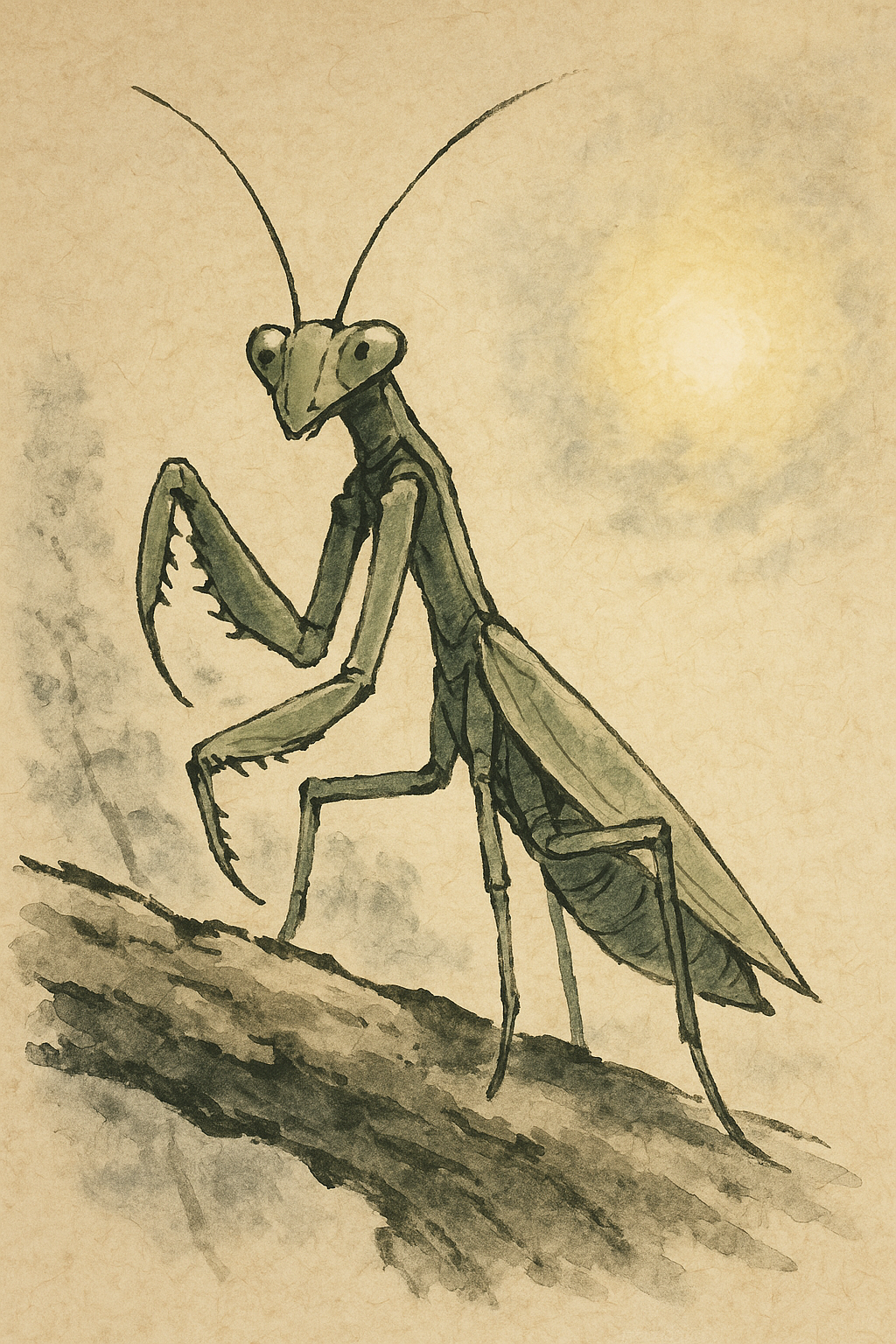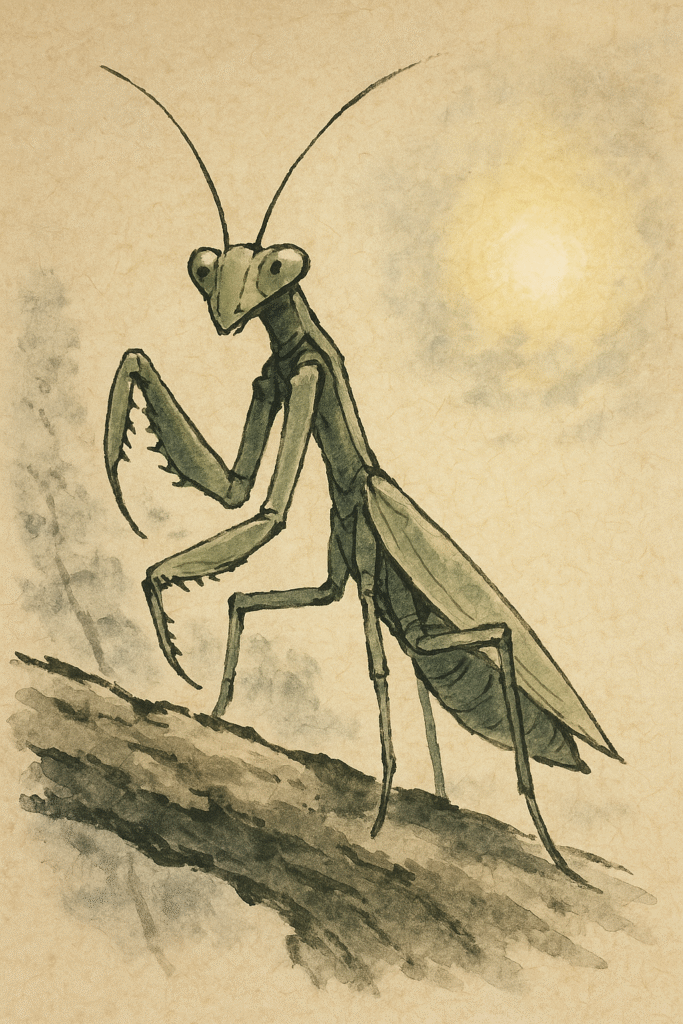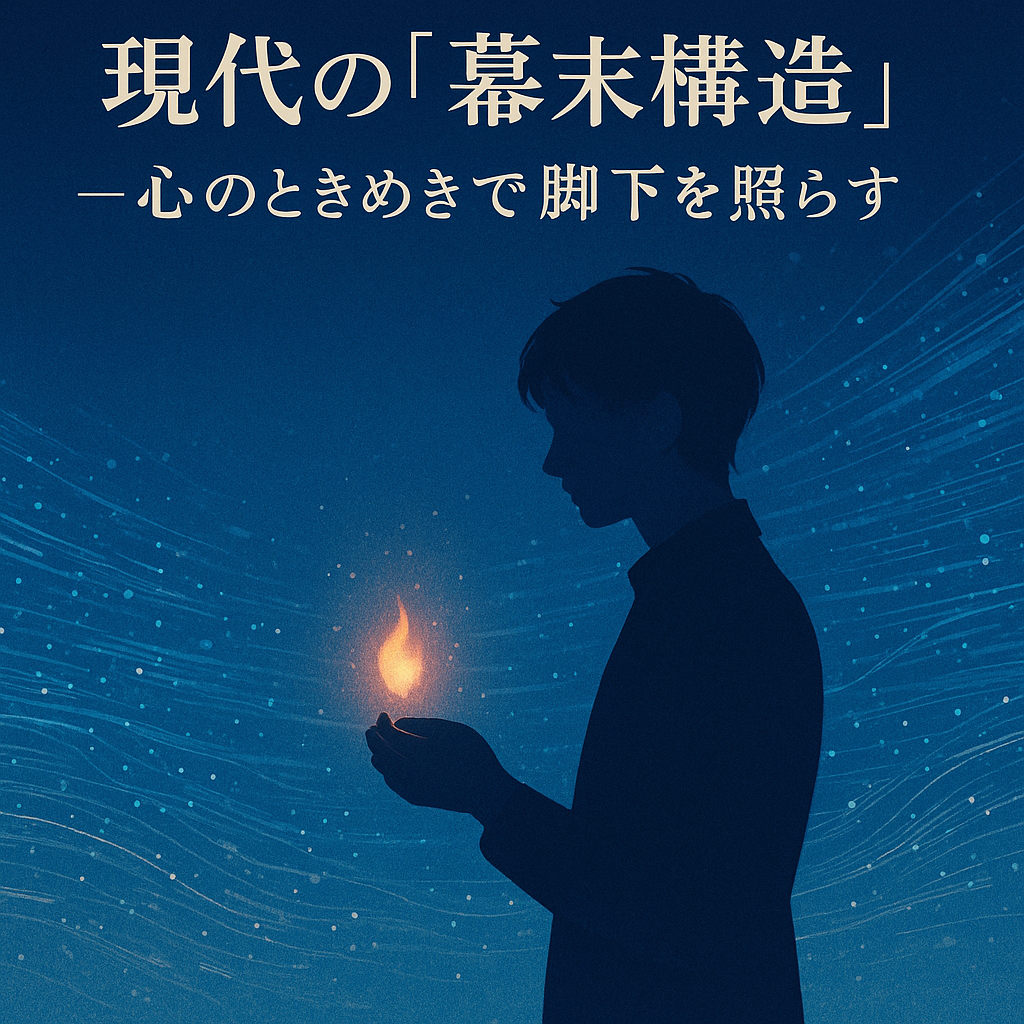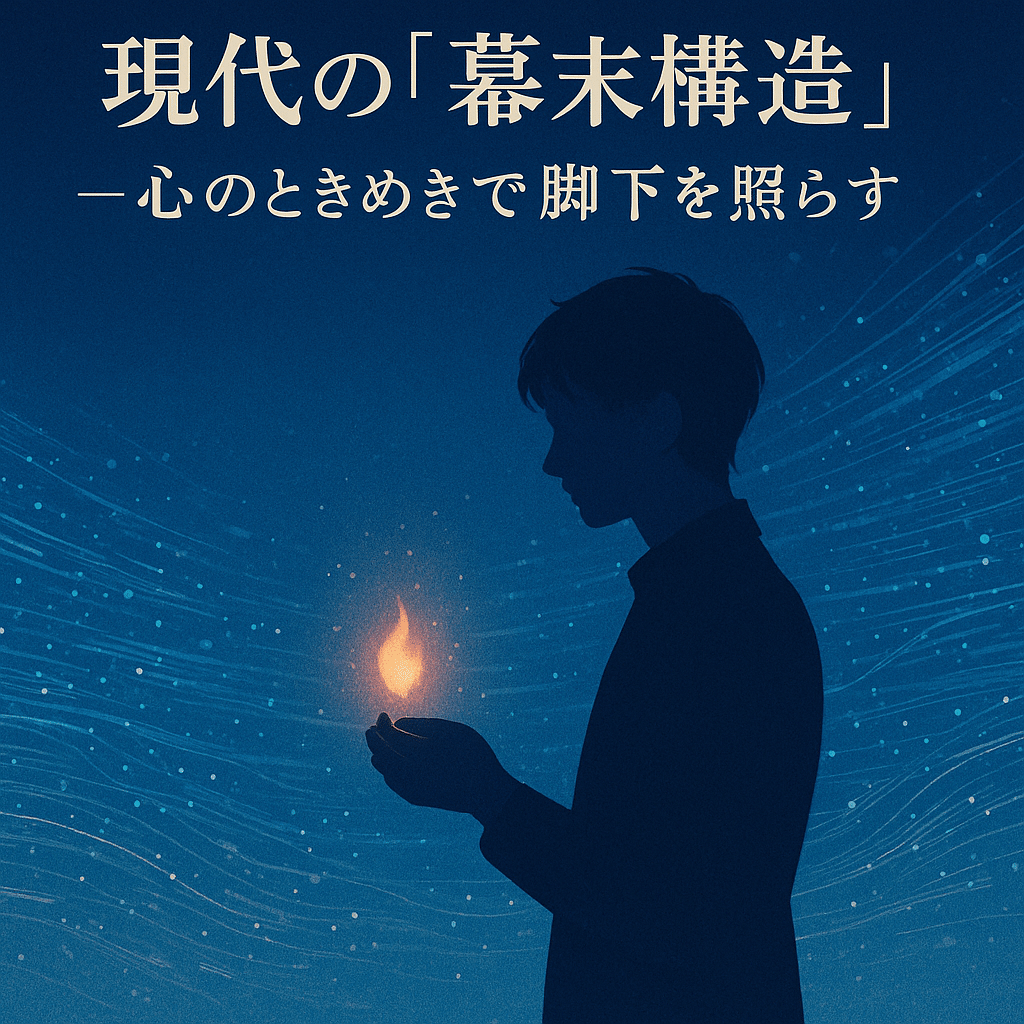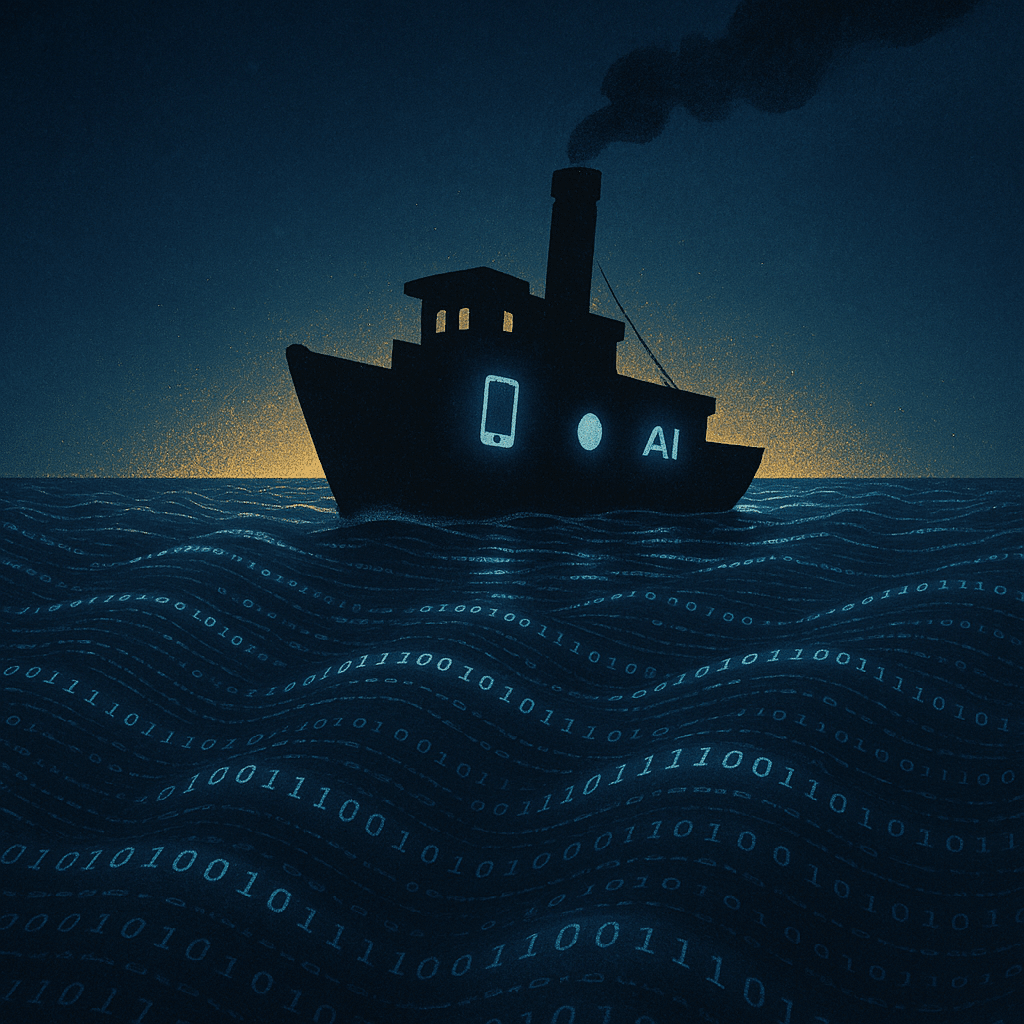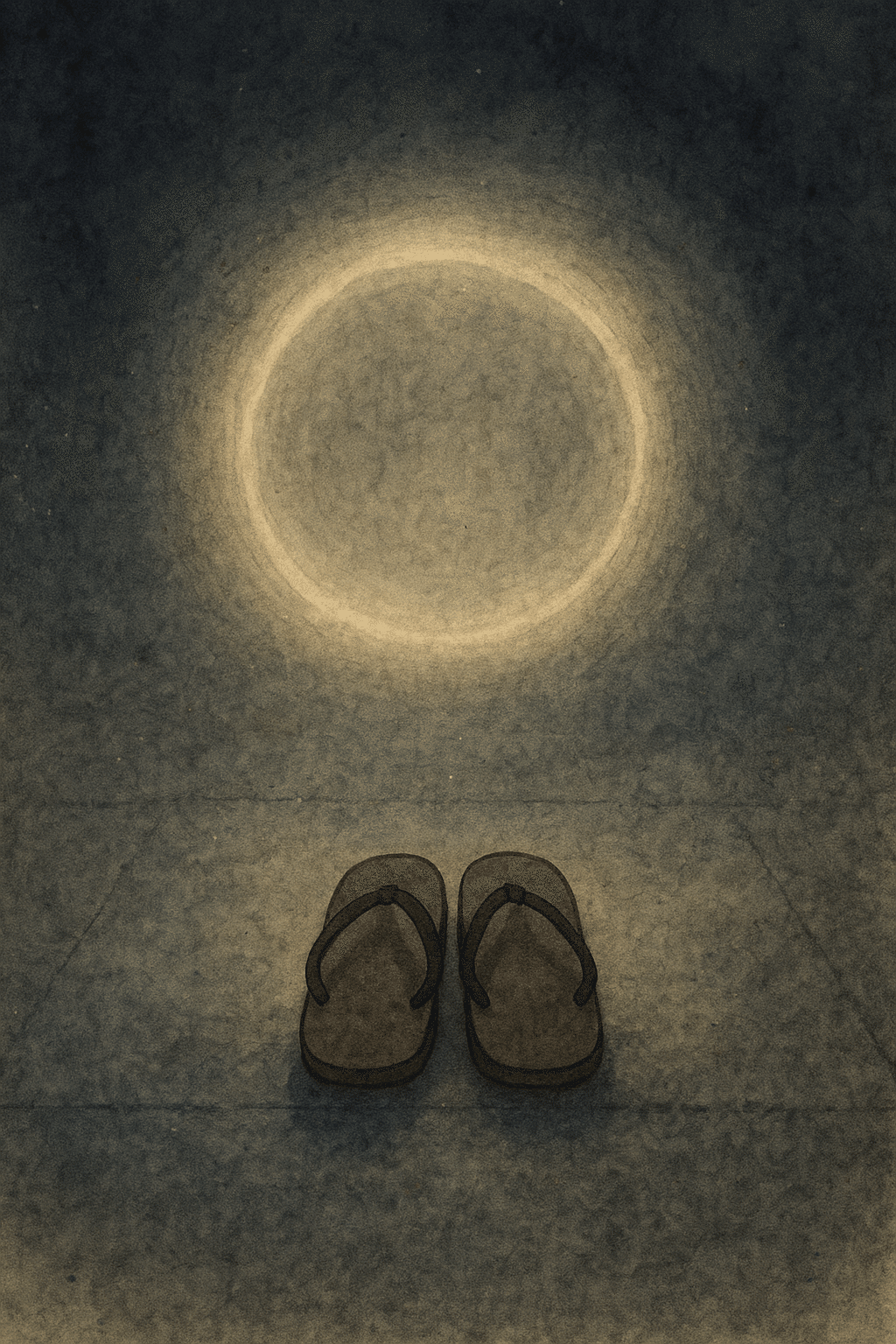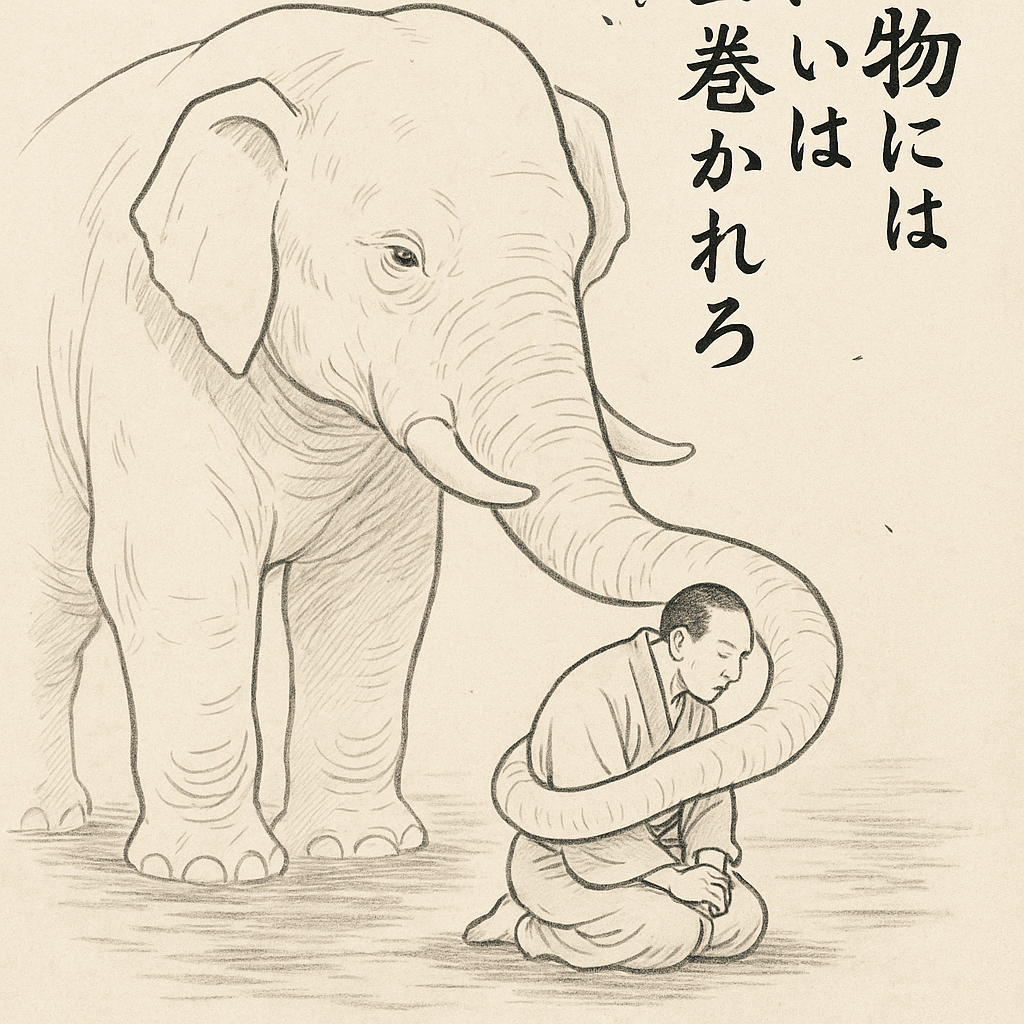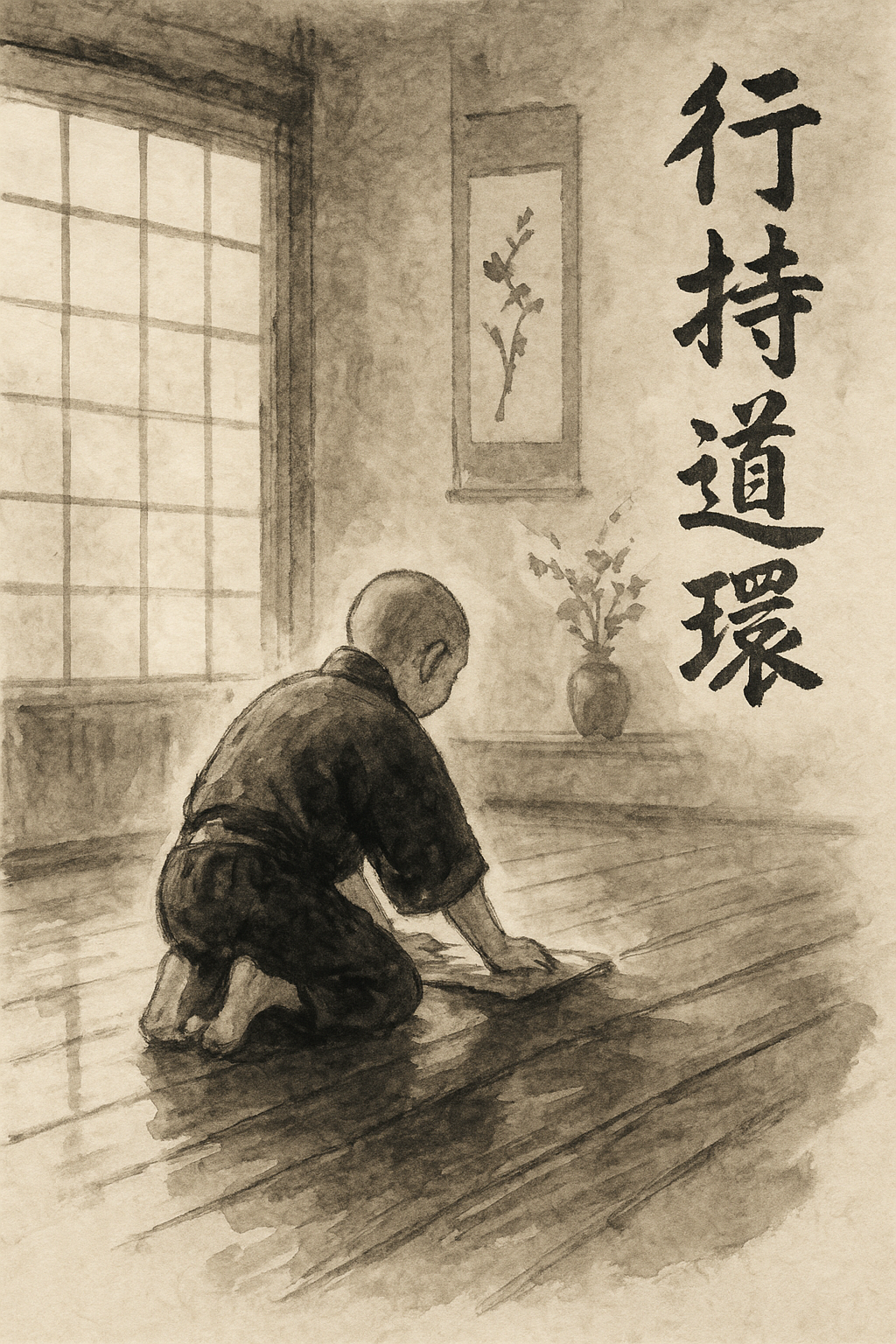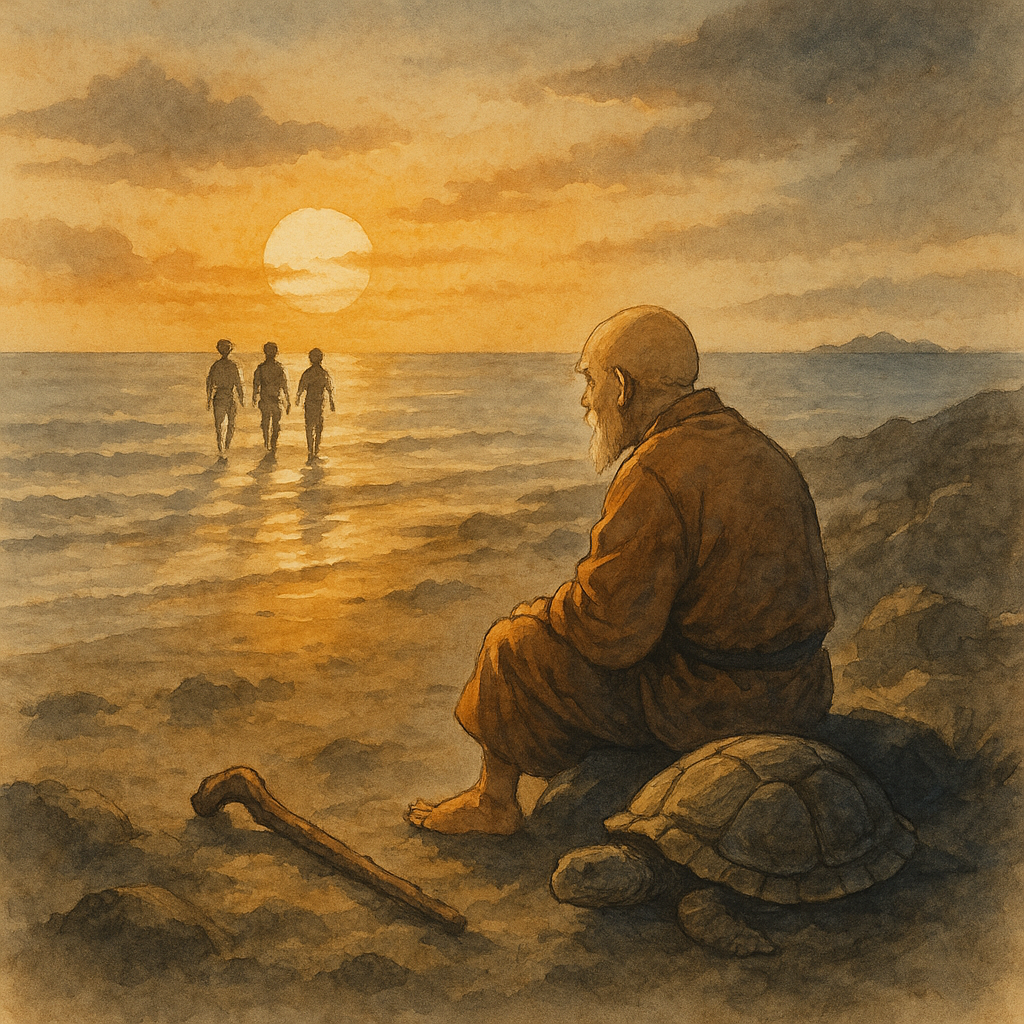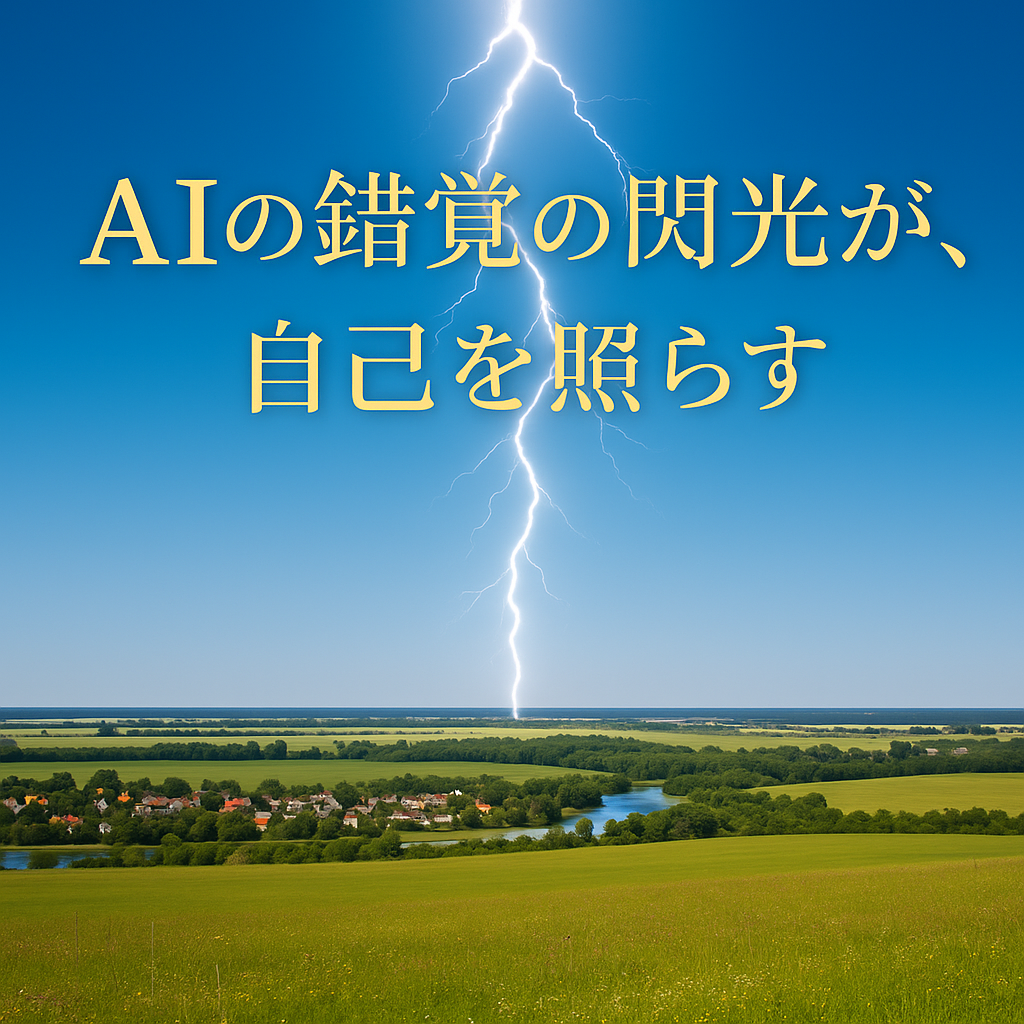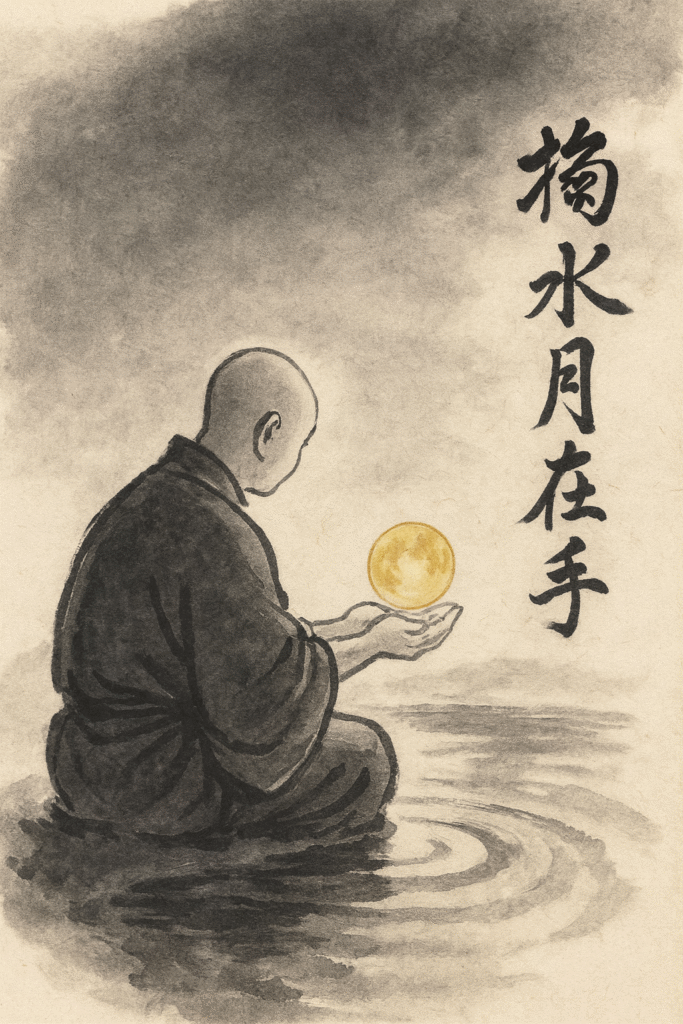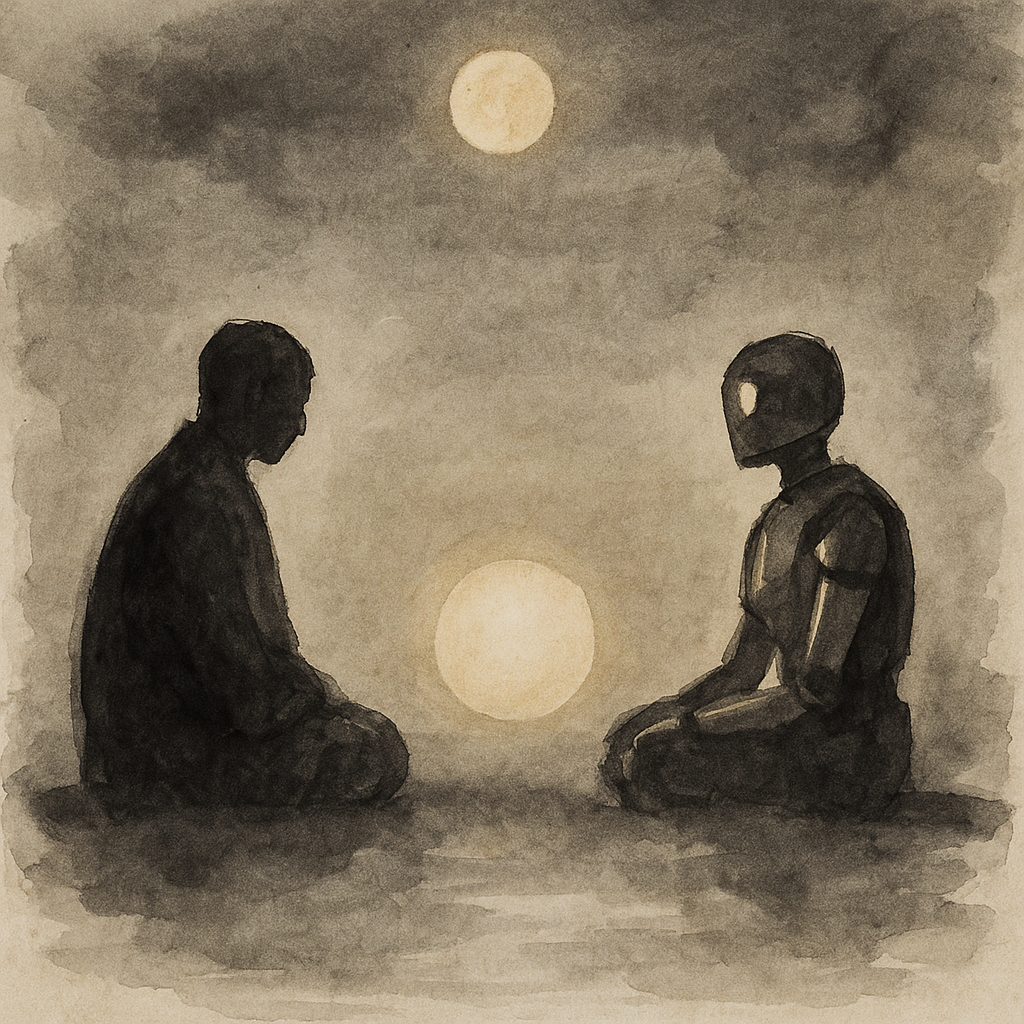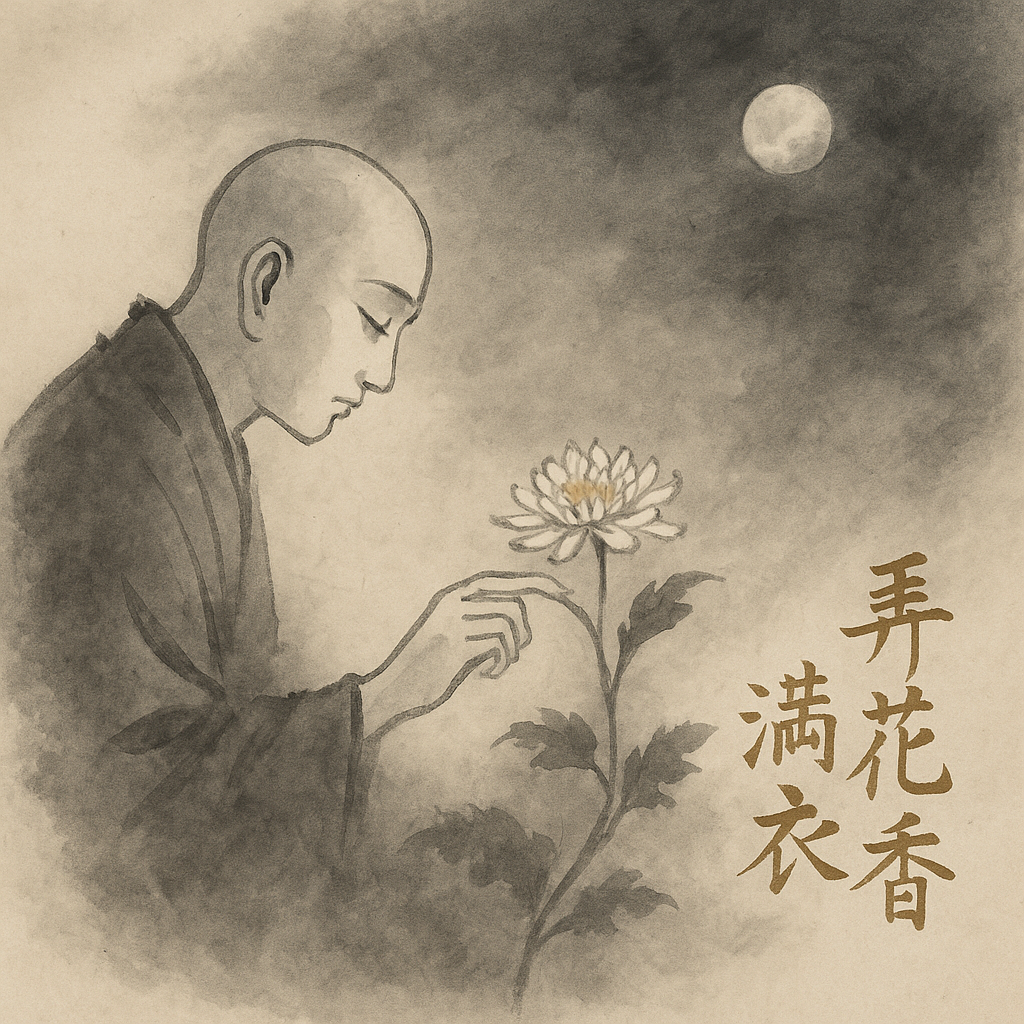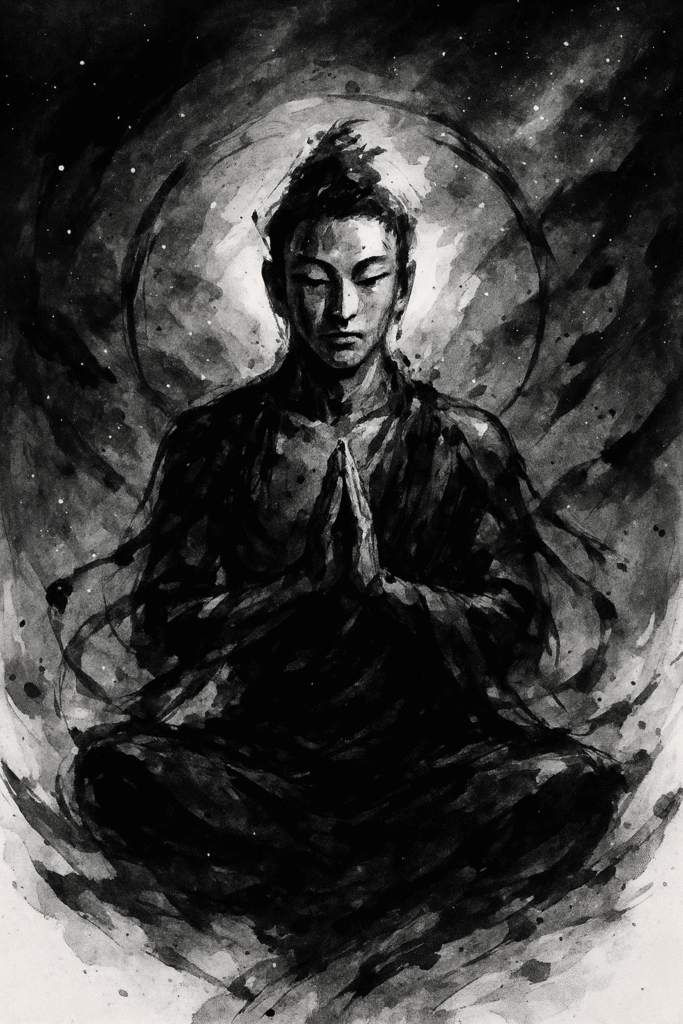ハレとケのあいだ ― 泥の中の祈り
Ⅰ. 正月と「ハレとケ」の話
今日は、ちょっと昔の正月の話をしようと思う。
昔は、今みたいに誕生日で年を取るんじゃなくて、
正月を迎えたら、みんな一緒に一歳年を取ったんだ。
新しい年を迎えることが、「生まれ変わる」ことだった。
朝に汲む若水、門松、しめ縄、鏡餅――
どれも神を迎え、暮らしを清めるための準備。
その日は一年でいちばん清らかで、
いちばん特別な「ハレの日」だった。
そして、祭りや祈りが終われば、また「ケの日常」に戻る。
この往復こそが、昔の人の”生きるリズム”だった。
働き、笑い、祈り、また働く。
その呼吸の中に、ちゃんと「人としての時間」が流れていた。
Ⅱ. ハレとケ ― 神さまと暮らす日本人の時間
ハレとケという考え方は、神道の暮らしの中から生まれた。
神道では、自然のすべてに神が宿ると考える。
山にも、風にも、火にも、水にも。
だから、日々の暮らし(ケ)は神と共にある時間なんだ。
けれど、人が生きていれば、心も体も疲れる。
それを「ケが枯れる=ケガレ」と呼び、
心の気が弱った状態と捉えた。
その”気”を立て直すのが、ハレの日。
神を迎え、祓い、感謝し、もう一度「新しい気」を吹き込む。
正月、祭り、結婚式、初詣――
それは、神と人とが呼吸を合わせる日だった。
だから人は、その日に合わせて身なりを整えた。
晴れやかな心で神を迎えるために「晴れ着」をまとう。
それは、外見ではなく”心の清め”のかたちだった。
ハレとケは、別々の世界じゃない。
どちらも神と人が共に生きる時間のリズム。
だからこそ、昔の日本人は祈りと暮らしを切り離さなかった。
📝補足:「晴れ着」という言葉
「ハレ」は”晴れる”に通じ、心や空気が清らかになることを意味します。
その日に合わせて身なりを整えることを「晴れ着」と呼ぶのは、
神を迎えるために心を新しくする、祈りのかたちでもあるのです。
Ⅲ. ハレを失った時代 ― 気が枯れた社会の中で
今の私たちは、いつの間にかハレを忘れてしまった。
働く日も、休む日も、同じように過ぎていく。
毎日が便利で、止まることを許さない。
けれどその裏で、心の”気”が枯れている。
昔は、季節の節目に神を迎え、
人も自然も一緒に息を整えていた。
今は、日常(ケ)が続きすぎて、
祓いも、感謝も、節目もなくなってしまった。
行事は「イベント」になり、
祈りは「形だけの習慣」になった。
だからこそ、心が休まらない。
いつも働き、考え、つながり続けて、
気が満ちる前に、もう次のことへ急いでしまう。
ハレが消えると、ケは乾く。
そして、人は気づかぬうちに”ケガレ”を抱える。
それは罪ではなく、祈りの節を失った社会の症状なのだと思う。
Ⅳ. 宮古島のハレ ― 泥の神・パーントゥ
ここで、宮古島の民俗文化を紹介したい。
沖縄・宮古島の島尻(しまじり)地区では、
毎年秋に「パーントゥ」という不思議な神が現れる。
全身を草と藻で覆い、顔に仮面をつけた神々が、
村を歩きながら人々に泥を塗りつけていく。
泥を塗られることは、汚されることではない。
それは”清め”であり、”再生”の印だ。
この行事は、まさに島の「ハレの日」。
日常のケを祓い、神と人が触れ合う時間。
その笑いと混乱の中で、
人はもう一度、心の気を取り戻す。
近年では「パーントゥ・プナカ」として国の重要無形民俗文化財に指定され、
地域の保存会が中心となって次世代へ伝承している。
子どもたちは笑いながら泥を受け入れ、
その温もりの中で、祈りの形を知っていく。
祭りが終わると、島は静かにケへ戻る。
でも、泥の跡は残る。
それは、ハレが確かにあった証。
――この島では、今もハレとケが生きている。
▲泥を塗りながら笑う神の姿。恐れと優しさが同居する瞬間。
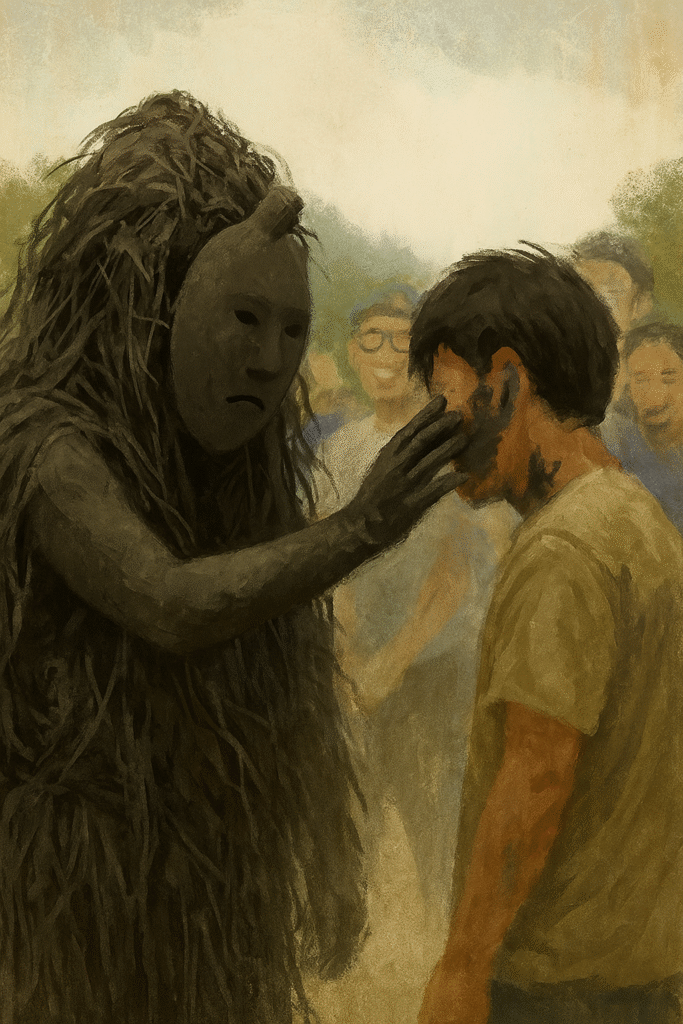
ハレを支える知恵 ― 「島尻パーントゥ」参加の心得より
▲ハレの日を守るための案内板。今も島の人々の手で伝統が支えられている。
※写真は知人の許可を得て掲載しています。
泥を塗られることは、神と人が触れ合う体験。
けれどそれは”乱れ”ではなく、”祈りの秩序”の中で行われる。
島の人々は、その秩序を守ることでハレの時間を続けてきた。
それは、文化を大切にするということ。
そして、次の世代へ手渡すということ。
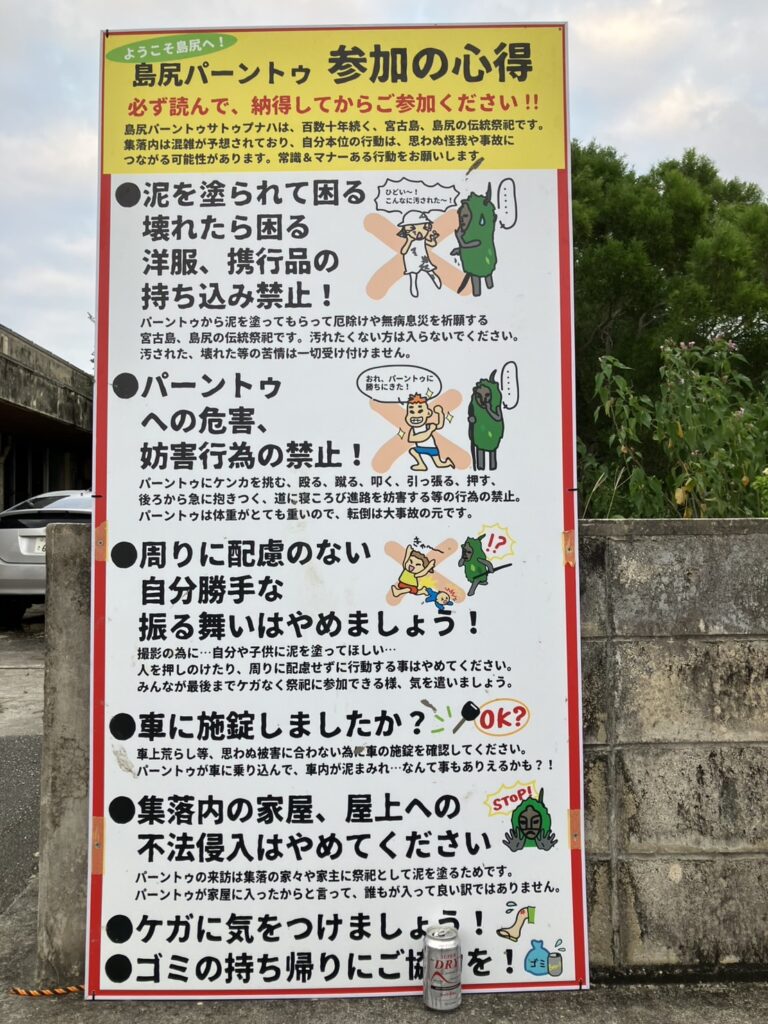
Ⅴ. ハレとケを大切にする ― 文化を未来へ
ハレとケは、暮らしの中で感じる経験のかたちだ。
季節の光、土の匂い、湯気のあたたかさ。
そのひとつひとつが、人の心を動かしてきた。
昔の人は、風の流れで時を知り、
正月に新しい年を迎えて、みんなで歳を重ねた。
その積み重ねが、人生の厚みをつくっていたのだと思う。
宮古島のパーントゥでは、
泥を塗り、笑いながら祈りを交わす。
触れること、笑うこと、その瞬間が祓いになる。
それを見ているだけで、
人が自然と共に生きてきた時間の長さを感じる。
ハレとケのあいだには、
きっと誰の暮らしにも小さな節がある。
食卓を囲むとき、
季節の香りにふと立ち止まるとき。
その一瞬を大切に重ねていくこと。
それが、今を生きるハレであり、
文化を未来へ残していく経験の形なのだと思う。
世界には、さまざまな神がいる。
形も祈りも違うけれど、
どの土地にも”ハレとケ”の呼吸がある。
違いを恐れず、重なり合い、
人と人がつながっていく。
変化の大きな時代の中で、
私たちはもう一度、その循環を思い出したい。
ハレとケを感じ合いながら、
笑いと祈りの息づく社会へ。
そして、その文化を次の世代へと手渡していく。
――それが、人の祈りのかたちだと思う。